バイクに乗っていてよく思うのが、「バイクの駐輪できるスペース、少ない」ってこと。
スレッズで少しバイクの駐輪スペースについて触れた投稿がありまして。
何気なくつぶやいたのですが、1万件以上の閲覧と30件以上のコメントが寄せられましたが、ご意見を見ていて、結構多かったのが「バイク駐輪場を取り巻く環境への不満」です。
・自動車の駐車スペースに停めていたら、自動車側から文句を言われた!
・50㏄以下のバイクは停めるところいっぱいあるのに、それ以上の排気量のバイクの駐輪スペースが少ない!
・駐輪スペースが小さいから、大型バイクじゃ入れられない!
など。
バイクの駐輪できるスペース、少ないですよね(Instagramリンク)
不満が寄せられる理由について、ちょっと調べてみました。
おそらくですが、法律上の問題と、バイク自体の問題の2つが大きいです。
法律上の問題としては、駐車場法では51㏄以上のバイクはすべて「自動車」扱いとなり、50㏄以下は「自転車法」のくくりになります。車両区分については、後述する道路交通法がベースとなっているでしょう。
また、排気量でバイクの区分をする法律が道路交通法と道路運送車両法と2つあり、微妙に区分が違い、これも混乱の要因と思われます。
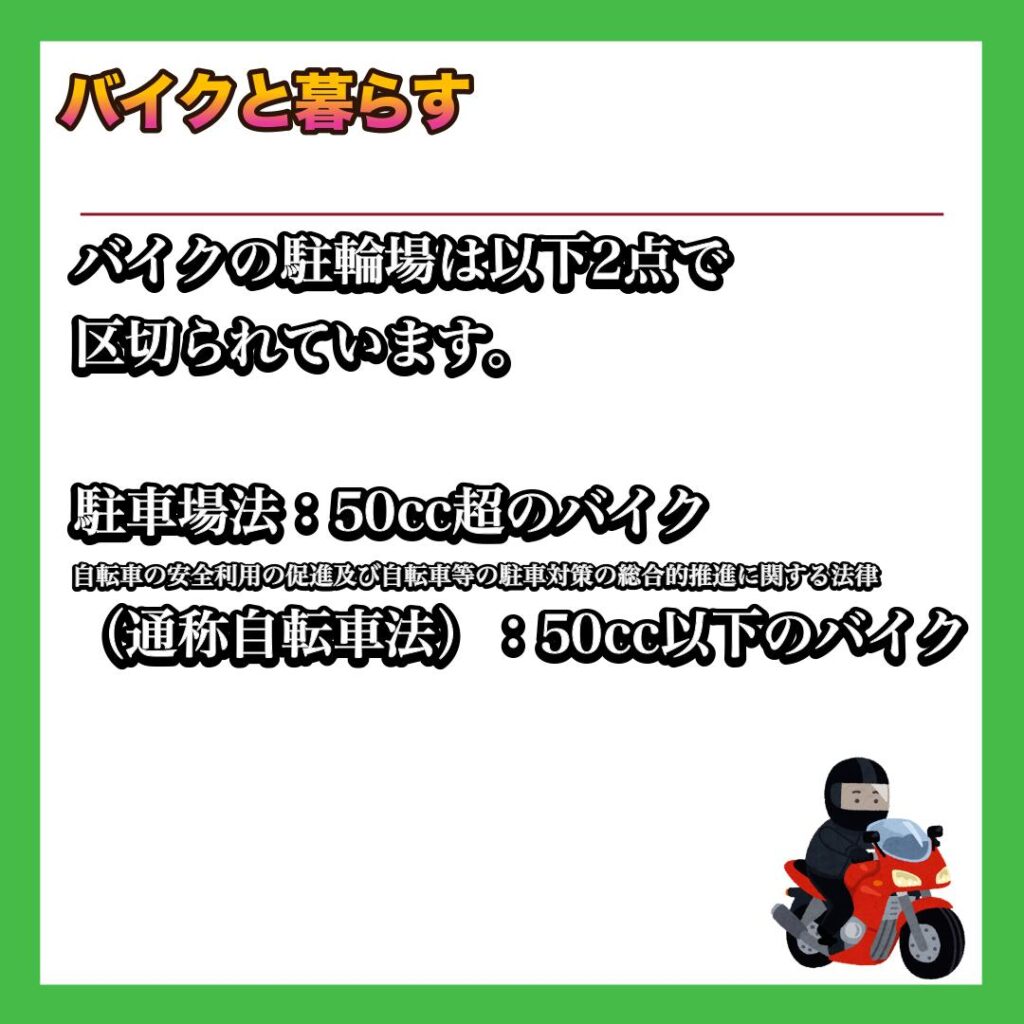
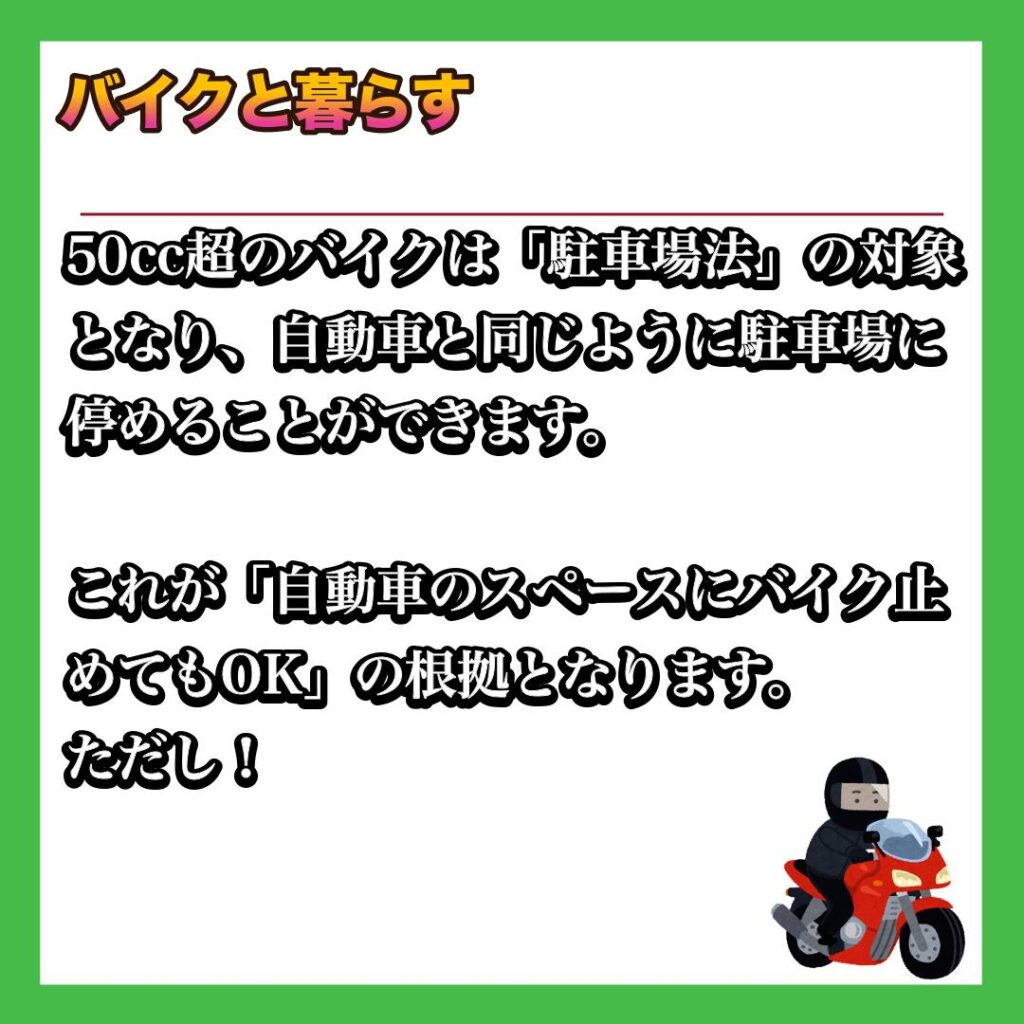
【バイクの車両区分】
道路交通法では、50cc以下は「原動機付自転車」、50cc超~400㏄以下を「普通自動二輪」、400cc超を「大型自動二輪」と区分しています。
道路運送車両法ではもう少し細かく区分されており、50cc以下は「第一種原付」、50㏄超~125㏄を「第二種原付」、125㏄超~250㏄以下を「軽二輪(二輪の軽自動車)」、250cc超~400㏄以下および、400cc超を「小型二輪(二輪の小型自動車)」となります。
もう、この時点でややこしいですね。
【免許区分】
道路交通法では免許の区分も異なりまして、50cc以下は「原付免許」、50cc超~125㏄以下は「普通自動二輪の小型限定免許」、125超~400cc以下で「普通自動二輪免許」、400cc超で「大型自動二輪免許」としています。
道路交通法の中で、バイクの免許区分と車両区分が異なっており、さらに道路運送車両法でも、車両区分が違うというややこしさ。
もう少しわかりやすくしてほしいですよね。
免許区分を道路交通法の車両区分に合わせてしまうか、その逆か。
あるいは道路運送車両法の定義に道路交通法のバイクの区分を合わせるとか。
個人的には免許区分に道路交通法・道路運送車両法の両方の車両区分を合わせるのがお勧めですね。税金、車検の有無とかは運用でカバーできないかなぁ、なんて思っています。
道路運送車両法の区分に従うと、125cc以下は自動車ではなく原動機付き「自転車」なので、自転車駐輪場に自転車として駐輪できる。だから、125cc以下に限定されたバイクの駐輪スペースが多い。
50㏄超のバイクは「自動車」という扱いになるので、自動車のスペースに停めることが正しい運用になりますが、あまりこの事実が一般に知られていない。
これが法律上の問題ですかね。

バイク自体の問題として、駐車スペースが小さい!問題については、明確な基準がバイク駐輪場では無いので、大体80㎝×1.5㎡くらいの125㏄の原チャリが入るくらいの設定でバイク駐輪スペースが作られているからではないか?と予想しました。
バイク自体の数が自動車と比べて少数で、車のようにボディサイズが明確に決まっている乗り物でもなく、車体の大きさがバイクごとにまちまちであるという、バイク特有の問題もあります。そのため、駐輪スペースへの不満が出やすいのだろうと推測します。
ここは、駐車場法などでバイクの駐輪スペースの推奨サイズを国から設定してもらったほうがいいですね。「横1.2m×縦2.0mをバイク用駐輪スペースの標準サイズとする!」みたいな。どうでしょうか?
自動車用の駐車場にバイクが駐車禁止なのは駐車場設置者の意向によるところが大きいようです。確かに自動車駐車場がプレート式だとバイクを傷つける可能性が高く、ゲート式だと、ゲートを通らずタダで駐車されてしまう。設備が自動車用のため、バイク入場NGにしている駐車場が多い。でも、ここは…仕方ないですよね。駐車場設置者の意向に従いましょう。
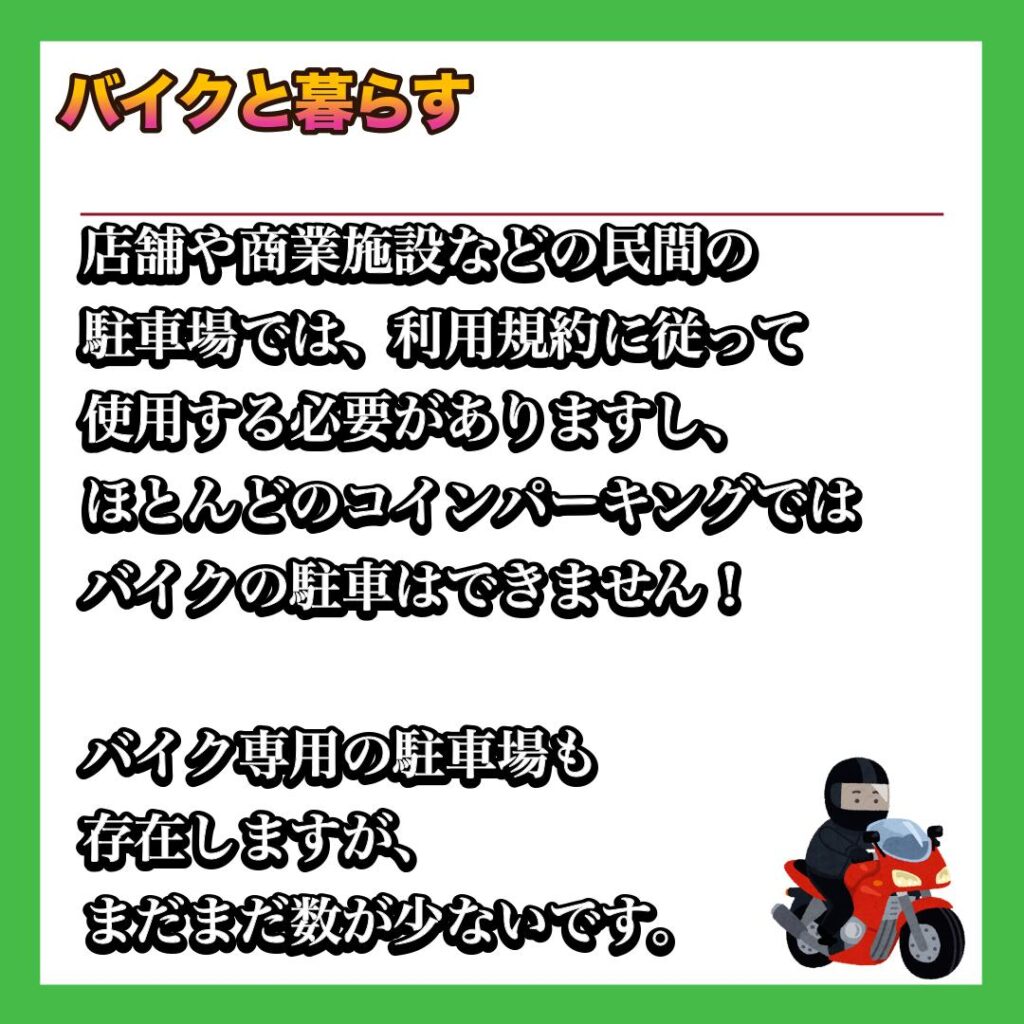
バイク駐輪場については、
①そもそも設置が義務付けられていない。
②ライダーの数が少ない。
2つの理由から、あまり設置されていないのでしょう。
駐輪場を増やすためにはバイク駐輪場が必要だ!とライダーが声を上げ続けるしかありません。
今回は、以上です!

